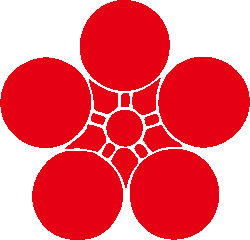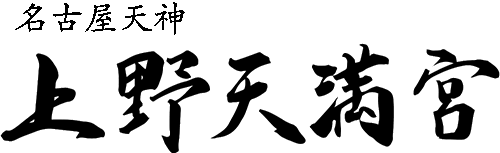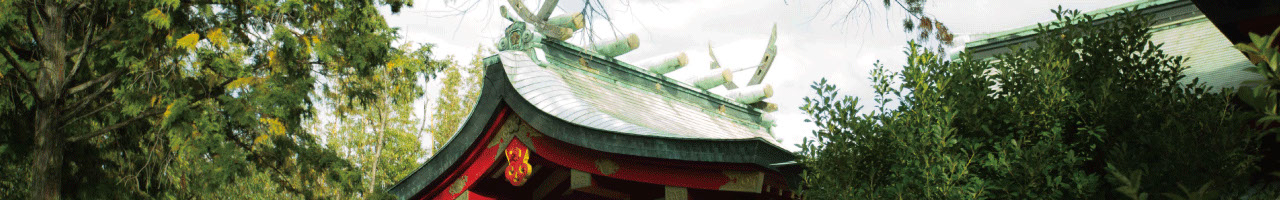
上野天満宮とは
上野天満宮の由緒
およそ千年前の平安時代中期に陰陽師・安倍晴明の一族がこの地に住んだ折、菅原道真公を慕ってその御神霊をお祭りされたのが上野天満宮の起源と伝えられています。
上野天満宮にお奉りされる菅原道真公が、九州の太宰府にて亡くなられて平成14年には1100年が過ぎました。こころざし半ばにして無実の罪を背負い京都から追いやられた天才学者の無念を償うため、菅原道真公の墓所の上に太宰府天満宮が作られました。その後、100年弱した頃、同様に京都を追われた花山天皇に仕えていた陰陽学者の安倍晴明(920~1005)一族の一部が、名古屋の名古屋市千種区清明山に移り住みました。自らの境遇と照らして菅原道真公の心情を儚く思い、上野天満宮(現在地には、矢田川の氾濫から江戸時代に移動)を建て、菅原道真公を手厚く奉りました。そしてその思いがかない、安倍一族は一部を当地に残して無事に京都に戻ることが出来たそうです当時の中国は、学問や政治の手本として、日本人のあこがれでした。菅原道真公も安倍晴明も日本の代表的な勉強家でしたから、彼らの理想は、時として日本の権力への批判とうつることがあったのでしょう。しかし「正義は勝つ。努力は必ずむくわれる」のですね。彼らの理想があったからこそ今の私たちがあるのだと思います。仕事に勉強に励んでください。必ず成果は現れます。

上野天満宮 年間祭典
一月 一 日 一番祈祷・歳旦祭
一月 十五日 左義長祭・うそかえ神事
一月 二十五日 初天神祭
二月 三 日 節分祭
二月 二十五日 御命日祭
三月 二十五日 祈年祭
六月 二十五日 御誕辰祭
七月 十五日 天王祭・茅輪神事
九月 二十三日 晴明祭
十月第四土曜日 宵宮祭
十月第四日曜日 例祭
十一月二十四日 愛宕社祭
十一月二十五日 新嘗祭
十二月二十五日 納め天神祭
毎月 二十五日 月次祭
学問・除災招福の守り神
学問の神で知られる菅原道真公をお祀りしています。毎年受験シーズンには沢山の学生等が合格祈願に訪れます。
道真公の人生は過酷でしたが、その生き方は誠実で我々の生き方にも多くのヒントを与えてくれます。また道真公は死後なお冤罪をそそぎ名誉を回復されたことから、災を除き福を招く『除災招福の神』として崇められるようにもなりました。道真公は藤原氏の策略に遭い太宰府に左遷された事は有名ですが、梅の花をこよなく愛され、太宰府での死に際し京都の梅が、菅公を偲んで太宰府にむけて飛来したとされる「飛梅伝説」などが今に伝えられています。それ以外にも、各地に数々の伝承が残り、庶民生活の中に天神信仰が親しみある存在として受入れられている事が伺い知れます。

菅原道真公
平安時代中期の華やかな王朝時代に活躍した実在の人物です。父是善、祖父清公と代々文章博士となった学者の家柄でした。文学者で政治家でもあった彼は、貞観四(862)年文章生、同19年文章博士となり、以後、宇多天皇の信任を得て、藤原氏の勢力を牽制するために重用されました。寛平三(891)年蔵人頭。同六年遣唐使に任命されましたが、大陸文化から得るところが少なくなったことや、航海の危険性を力説した彼の意見から遣唐使制度そのものが中止されました。
その後、権大納言を経て昌泰二(899)年右大臣となり、同四年に突如藤原時平の策謀から大宰府に左遷されてしまい、ついには延喜3年2月25日、無実をはらすことなく太宰府にて死去、享年五十九歳でした。編書に『日本三代実録』『類聚国史』、詩文書『菅家文草』『菅家後集』等があります。死後、天変地異や管公を陥れた者の怪死によって管公の冤罪がそそがれ、朝廷からは左遷の証書の破棄、さらには正一位太政大臣を追贈されるなどして無実が証明されました。
後世、管公の誠実な生涯が慕われ、天神さまとして全国に崇敬されています。
梅の花は天満宮のシンボルとして扱われています。道真公は五歳の時「美しや紅の色なる梅の花 あこが顔にもつけたくぞある」と詠んで人びとを驚嘆させましたが、太宰府への左遷が決まり失意の内に京都の自宅の梅を見て「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花 あるじなしとて春な忘れそ」と詠まれました。道真公は梅の可憐さをこよなく愛されたと伝えられています。また、梅干しのタネの中には天神様がいらっしゃるので食べずに、タネだけを神社に返す習慣の地方があります。その他にも管公の自宅の庭の梅が遠く太宰府の管公を慕って飛んだ来たという「飛び梅伝説」などもあり、天神さんと梅にまつわる話は尽きません。
天神信仰
元々は稲妻の事を指していたようです。雷光が、天の恵みの雨を降らせ、農業を守護する神となったわけです。しかし、地震や火事などの災をもたらす神として恐ろしい一面も持っていましたので、「たたり神 ー天神」として、無実の罪のまま亡くなった道真公の霊が怨霊となり、自分を陥れた藤原氏の一族を、雷を使って横死させたのだと考えられました。当時、彗星の飛来、雷災といった天変地異が度々起きたこともあり「天神とは菅原道真公」と解釈されるようになりました。
道真公の死後50年の間に彼の霊が数度託宣し、その霊の威力が当時の人々に理解された結果、古くから天神祠のあった北野に菅原道真公の霊が祀られ、「大政威徳天、天満大自在天」と呼ばれました。
その後怨霊がしずまり穏やかになると、災難を除き福を招く「除難招福」の神様と慕われるようになりました。また、天才と云われた頭脳明晰な道真公の徳から学問向上を目指す祖神とあがめられるようになり、勉強する子供たちの守護神に変化しました。

天満宮と牛
天満宮と名の付く多くの神社には牛の像があります。これは道真公の生まれ年が承和12年6月25日、この日は乙丑(きのとうし)に当たるためとか、道真公のご遺体を運ぶ途中に牛車がどうしても動かなくなり、道真公のご意志と解釈してその地に埋葬しました。その地が安楽寺となり、現在の太宰府天満宮となった事から、牛を道真公の使いとする説。天満自在天神という名前に由来する説。大自在天とは八本の腕と三つの眼を持ち白い牛に乗っていると云われ、このため天神様も牛とセットする考えです。
牛像の頭をなでると賢くなるとか体の悪いところをなでると良くなると言われています。上野天満宮の境内に二つの「なで牛」がいます。是非頭をなでてあげてください。